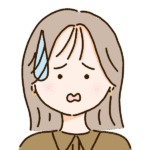
地震のあとから、うちの猫の様子がなんだか変…



ずっと隠れて出てこないし、ごはんも食べてくれない…これって大丈夫なの?



前みたいに甘えてこなくなった。どう接してあげたらいいんだろう…
そんな不安を感じている飼い主さん、じつはとても多いんです。
地震のあとに猫の様子が変わるのは、めずらしいことではありません。
この記事では、地震後に見られる猫の変化と、飼い主さんができるサポートの方法をやさしく解説します。
怖かったのは、猫も同じ。
まずは猫の気持ちを理解してあげることから、少しずつ心を整えていきましょう。
- 地震のあとに猫の様子が変わる理由
- よくある行動の変化とその意味
- 飼い主ができる安心サポート方法
- やってはいけないNG対応
- おうちでできるストレスケア7選



焦らなくて大丈夫。
少しずつ、猫の“安心”を取り戻していきましょう。
猫が地震後に様子がおかしくなるのは普通?
結論から言うと、地震のあとに猫の行動が変わるのは、めずらしいことじゃないんですよ。
病気でも性格が変わったわけでもなくて、“怖かった気持ちがまだ残っているだけ”なんです。
猫が地震のあとに隠れたり、ごはんを食べなかったり、鳴き続けたりするのは、ごく自然な反応。
たいていの子は時間がたつと、少しずつ落ち着いていきますよ。
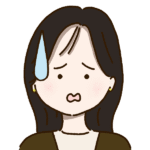
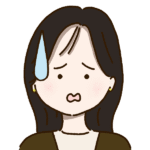
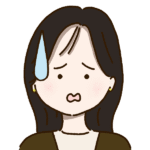
うちの猫2匹は、元々地震の少ない九州猫。
だから関東に引っ越して地震を感じたときは、かなりビックリしていました。
でも今では、地震4くらいでも寝ています(笑)
でも猫ちゃんの様子があまりにもおかしいと、「どうしちゃったの?」と心配になりますよね。
そこでまずは、地震後の猫の変化は“よくあること”なんだと知っておくことが大切なんです。



次の章で、
地震のあとによく見られる7つの行動の変化を、ひとつずつ見ていきましょう。
猫は地震後にどんな行動をする?7つの変化
ここからは、地震のあとによく見られる猫ちゃんの7つの変化を、
理由といっしょに見ていきましょう。



知っておくことで、飼い主さんが慌てず対応でき、
猫ちゃんが安心できるようになります。
地震後の変化①急に隠れて出てこなくなる
地震のあと、急に押し入れやベッドの下に隠れて出てこなくなる子がいます。
それは「怖かった」「まだ安全かわからない」と感じているからなんです。
猫はもともと警戒心が強くて、ちょっとした音や空気の変化にも敏感。
一度怖い思いをすると、“安心できる場所”にこもってじっと様子をうかがうことがあるんです。
- 押し入れや家具のすき間など、暗くて狭い場所に隠れる
- 名前を呼んでも返事をしない・出てこない
- しばらく動かず、じっと息をひそめている
こうした行動は、地震の怖さをしっかり覚えているからこそ。



「また揺れるかも…」という不安が残っているんですね。
地震後の変化②ごはんを食べなくなる
地震のあとから、急にごはんを食べなくなる子もいます。
「落ち着かない」「安心できない」と感じているサインなんです。
猫は環境の変化にとても敏感。
揺れたあとの音やにおい、人の緊張した空気を感じ取って、食欲がストップしてしまうことがあります。
- お皿の前まで来ても、においをかぐだけで食べない
- お気に入りのおやつにも反応がない
- 食事の時間になっても、姿を見せなくなる
これは「食べたくない」わけではなくて、心が落ち着かない状態なんです。



猫にとって“食べる”ことは安心の証。
だからこそ、不安が続くと食欲もいったん止まってしまうんです。
地震後の変化③鳴き続けたり、夜鳴きをするようになる
地震のあと、いつもより鳴くようになったり、夜になると大きな声で鳴く子もいます。
「どうしたの…?」と心配になりますよね。
猫にとって“鳴く”ことは、気持ちを伝える大切な手段なんです。
地震で怖い思いをしたあと、不安や寂しさを鳴き声で表していることがあります。
- 夜になると落ち着かず、鳴きながら部屋を歩き回る
- 飼い主の姿が見えないと、すぐに鳴き出す
- いつもより声が大きく、しつこく鳴き続ける
これは「かまってほしい」というより、安心したい・そばにいたいという気持ちのあらわれなんです。



「鳴く=わがまま」ではなく、心のSOS。
地震で感じた不安が、まだ少し残っている状態です。
地震後の変化④トイレの失敗・粗相が増える
地震のあとから、トイレ以外の場所でおしっこをしてしまう子もいます。
「いつもはきちんとできていたのに…」と、びっくりしますよね。
でも、これはわざとではありません。
地震のショックや環境の変化で、「トイレが安全な場所じゃない」と感じてしまうことがあるんです。
- トイレの前までは行くけど、中に入らずに出てしまう
- お気に入りの毛布やカーペットの上でしてしまう
- 落ち着かず、トイレの場所をウロウロしている
猫にとって“トイレ”はとても大切な場所。
そこに少しでも不安を感じると、体が自然に避けてしまうことがあるんです。



「失敗しちゃった」ではなく、「まだ怖いんだな」
そう思ってあげるだけで、見え方が少し変わりますよ。
地震後の変化⑤飼い主との距離が急に遠くなる
地震のあと、急によそよそしくなったり、距離をとるようになる子もいます。
「嫌われちゃったのかな…」なんて不安になりますよね。
でも、それは飼い主さんのことが嫌になったわけではありません。
猫にとって地震は「怖かった場所や音を思い出すきっかけ」になることがあるんです。
そのときそばにいた人や空気を、少しの間“怖かった記憶”と結びつけてしまうことがあるんですね。
- 近づくとスッと離れてしまう
- 名前を呼んでも返事をしなくなる
- 同じ部屋にいても距離を置いて座っている
これは「信頼がなくなった」わけではなく、“まだ少し怖い気持ちが残っている”だけなんです。



猫は安心できるようになるまで、自分のペースで距離を取ることがあります。
地震後の変化⑥逆にやたら甘えてくるようになる
地震のあと、急にべったり甘えるようになる子もいます。
「いつもよりそばにいたがる」「離れると鳴く」などの変化に気づくこともあるでしょう。
これは、猫が不安をやわらげようとしているサインなんです。
怖い思いをしたあと、「飼い主さんのそばにいれば安心できる」と感じて、いつも以上にスリスリしたり、膝の上から離れなくなったりします。
- ずっとついて回る・視線を離さない
- トイレやお風呂までついてくる
- 体をくっつけて寝たがる・抱っこをせがむ
いつもより甘えん坊になるのは、安心を求めている気持ちのあらわれなんです。
「怖かった」「ひとりになりたくない」という心の余韻が残っている状態ですね。



猫なりの「大丈夫?」のサインでもあります。
怖かった気持ちを、そばで少しずつ癒しているのかもしれませんね。
地震後の変化⑦ずっと落ち着かず、家中をウロウロし続ける
地震のあとから、ずっと家の中を歩き回って落ち着かない子もいます。
行ったり来たりして、なかなか休まない姿を見ると心配になりますよね。
これは、猫が「安全を確認しようとしている」行動なんです。
地震で揺れたり物が倒れたりしたことで、どこが安全なのかを確かめようとしている状態なんですね。
- 部屋を何度も行き来して、落ち着かない様子
- いつもと違う場所をくんくんと確認して回る
- 寝ようとしてもすぐに起きて歩き出す
猫は環境の変化にとても敏感で、「ここにいても大丈夫かな?」と確かめながら動いていることがあります。
落ち着かないように見えても、それは猫なりの確認作業なんです。



ウロウロするのは、不安だからこその行動。
「安全を探してるんだね」と、やさしく見守ってあげてくださいね。
猫の様子がおかしい…地震後に飼い主ができること3つ
先に説明したように、猫の様子が変わるのは決してめずらしいことではありません。
でも、見ている側としては「どうしてあげればいいの?」と戸惑いますよね。
そんなときは、「今の猫に必要なサポート」を3つのステップで考えるのがおすすめです。
無理に元の状態に戻そうとせず、猫のペースに寄り添うことがいちばん大切なんです。



少しずつ、安心を取り戻していけるように。
飼い主さんができることを、ここから一緒に見ていきましょう。
①まずは「時間が必要」と受け止める
地震のあとは、猫も心の中がざわついています。
すぐに元に戻らなくても、それは自然なことなんです。
猫は人よりも慎重で、環境の変化に敏感。
怖い体験をしたあと、安心を取り戻すまでに時間がかかる子も多いんですね。
- 数日〜数週間かけて少しずつ落ち着く
- 日によって元気だったり、不安そうだったりと波がある
- 飼い主の緊張や焦りも、猫は敏感に感じ取る
「早く元気になってほしい」と思うのは当然ですが、
焦って関わると、かえって不安を強めてしまうこともあります。



“時間が薬”という言葉は、猫にもあてはまります。
ゆっくり見守る気持ちこそが、いちばんのサポートなんです。
②小さな変化を記録しておく
地震のあと、猫の行動や表情が少しずつ変わっていくのを感じることがあります。
「昨日よりちょっと食べた」「鳴かなくなった」——そんな小さな変化が大切なんです。
猫は言葉で気持ちを伝えられないぶん、行動や食事・鳴き方でサインを出しています。
だからこそ、飼い主さんが“気づいたこと”を記録しておくと、猫の回復の流れが見えてくるんです。
- 「今日はごはんを完食した」など、日ごとのメモをとる
- 元気・鳴き方・隠れ時間などをざっくり記録する
- 気になる変化はスマホで動画や写真に残しておく
小さな記録でも積み重ねると、「少しずつ元気になってるんだな」と実感できるようになります。
不安な気持ちを整理するのにも役立つんですよ。



猫の“今”を見守ることが、いちばんの安心につながります。
焦らず、一歩ずつ。記録はその小さな歩みの証です。
③不安が続くなら迷わず動物病院で相談
地震からしばらくたっても、元の様子に戻らない…。
そんなときは、ひとりで悩まずに動物病院へ相談してみましょう。
猫のストレスや不安は、体の不調としてあらわれることもあります。
食欲の低下や嘔吐、下痢、鳴き続けるなどの変化が続くときは、
心だけでなく体のケアも必要なサインかもしれません。
- ごはんをほとんど食べない日が何日も続く
- 隠れたまま出てこない・鳴き止まない
- 下痢・嘔吐・排泄の変化が見られる
- たまに血尿になるときも
「これくらいで病院に行っていいのかな?」と思うかもしれませんが、早めの相談が安心への近道。
診てもらうことで、飼い主さんの不安もぐっと軽くなります。



“心配しすぎかな?”と思うくらいで、ちょうどいいんです。
猫も飼い主さんも、安心できる環境を取り戻すことがいちばん大切です。
そもそも地震後に猫の様子が変わる理由って?
「どうして急に隠れるようになったんだろう…」
「前と同じ家なのに、落ち着かないのはなぜ?」
じつは、猫が地震のあとに行動を変えるのにはちゃんと理由があります。
ここでは、地震後に猫の様子が変わる主な原因を、
「五感によるストレス」と「性格・経験の違い」の2つに分けて見ていきましょう。



「どうしてこうなるの?」がわかるだけで、猫の行動がぐっと理解しやすくなりますよ。
猫は五感でストレスを感じる|揺れ・音・におい
地震のストレスをいちばん強く感じるのは、人よりも動物かもしれません。
それは、動物が世界を「五感」で細かく感じ取って生きているからなんです。
特に猫は人の態度や環境の変化に敏感で、ダイレクトに体調に表われます。
私たちが「ちょっと揺れたかな?」と思う程度でも、
猫にとっては大地のうなり・空気の変化・家のきしみなどが全部伝わっています。
そのすべてが“安全かどうか”を判断する材料になるんですね。
- 揺れ:体の小さな振動にも敏感で、恐怖を強く感じやすい
- 音:物が落ちる音や地鳴りを記憶して、後からも怖がることがある
- におい:倒れた家具や埃、ガスなどの匂いが刺激になりやすい
こうした五感の情報は、猫の中で「怖い記憶」として残りやすいんです。
そのため、地震が終わっても落ち着かず、警戒が続くことがあります。



人には見えない“世界のざわつき”を、猫はちゃんと感じ取っているんです。
性格や過去の経験が原因である場合も
同じ地震を経験しても、平気な子もいれば強く怖がる子もいます。
それは、猫の性格やこれまでの経験の違いによるものなんです。
臆病な子や神経質なタイプの猫は、ちょっとした刺激にも大きく反応しやすい傾向があります。
また、過去に怖い思いをしたことがある猫は、地震の揺れをきっかけに記憶を思い出してしまうことも。
- もともと音や環境の変化に敏感な性格
- 過去に大きな音や地震を経験してトラウマがある
- 飼い主の不安な様子を感じ取って、同じように緊張している
つまり、「この子だけおかしい」のではなく、それぞれの性格と記憶の差なんです。
猫にも心の“感じ方の個性”があると考えてあげましょう。



怖がりな子ほど、安心を取り戻すのに時間がかかるだけ。
そのペースを尊重してあげることが、いちばんの理解なんです。
地震後に怖がる猫にやってはいけないNG対応3選
地震のあと、怖がる猫を見ていると「どうにか落ち着かせてあげたい」と思いますよね。
でもその気持ちからついやってしまいがちな行動が、猫の不安をかえって強めてしまうこともあるんです。
ここでは、“やさしさのつもりが逆効果になってしまうNG対応”を3つ紹介します。
猫が安心を取り戻すために、まずは避けたい行動を知っておきましょう。



ほんの少し意識を変えるだけで、猫が安心するスピードがぐっと変わりますよ。
NG対応❶無理に引っ張り出す・追いかける
地震のあと、隠れて出てこない猫を見ると「大丈夫かな?」と心配になりますよね。
つい「出ておいで」と手を伸ばしたくなる気持ち、よくわかります。
でも、怖がっているときに無理に引っ張り出したり、追いかけてしまうのは逆効果。
猫にとっては「また怖いことが起こった」と感じてしまい、
さらに強い警戒心を持ってしまうことがあるんです。
- 押し入れや家具のすき間から無理に引き出そうとする
- 隠れた場所をのぞき込んで何度も声をかける
- 出てこないことに焦って、部屋中を探し回る
猫にとって“隠れる”のは、安全を確かめるための時間。
無理に関わろうとすると、「安心の時間」を奪ってしまうことになります。



「まだ出てこなくても大丈夫」
そう思えるだけで、猫も少しずつ安心を取り戻していきますよ。
NG対応❷叱る・大きな声を出す
地震のあと、粗相や夜鳴きが続くと「もう!」とつい声を荒げたくなることもありますよね。
でも、その「叱る」「大きな声を出す」は、猫にとってさらに怖い出来事になってしまうんです。
猫は人の声のトーンや空気の変化にとても敏感。
大きな声を聞くと、「また何か怖いことが起きた」と感じて身をすくませてしまうことがあります。
- 粗相を見つけて「ダメでしょ!」と叱ってしまう
- 鳴き声が続いてつい「うるさい!」と怒鳴ってしまう
- 大きな物音を立てて驚かせてしまう
猫は言葉ではなく“雰囲気”で気持ちを感じ取る動物です。
叱られることで「また何か悪いことをした」と混乱してしまい、余計に心を閉ざしてしまうこともあるんです。



「落ち着いた声」と「穏やかな空気」こそ、猫にとっての安心。
今は“叱る時期”ではなく、“寄り添う時期”なんです。
NG対応❸環境をコロコロ変える
「落ち着かないみたいだから、環境を変えてあげよう」
そう思って、ベッドの場所を動かしたり、模様替えをしたくなることもありますよね。
でも、地震のあとの猫にとっては、“変化そのもの”がストレスになることがあります。
やっと安心できそうな場所を見つけたのに、また違う景色になってしまうと、
「どこが安全なのかわからない」と混乱してしまうんです。
- 落ち着かない様子を見て、ケージや寝床を何度も移動する
- 音やにおいを変えようと、部屋の配置をすぐ変えてしまう
- 新しいグッズや香りを一気に増やしてしまう
猫は変化にとても敏感な動物。
「何も変わらない安心感」こそ、地震後に必要な空気なんです。
一度落ち着いた環境は、できるだけそのまま保ってあげましょう。



“刺激より、安定”。
猫が安心できるペースを大切にしてあげてくださいね。
おうちでできる!猫のストレスを和らげる対処法7選
地震のあと、猫が落ち着かない様子を見ると
「少しでも安心させてあげたい」と思いますよね。
実は、特別な道具や大きな工夫がなくても、おうちの中でできる“心のケア”はたくさんあるんです。
ここでは、地震のあとに猫のストレスをやわらげるための
「今日からできる7つのケア」を紹介します。
どれもすぐに試せて、猫の“安心”を少しずつ取り戻すきっかけになりますよ。



猫のペースに寄り添いながら、少しずつ元気を取り戻せるように。
あなたの“やさしい手助け”が、きっと心の支えになります。
①猫が安心できる「隠れ場所」を用意する
地震のあと、猫が押し入れやベッドの下に隠れて出てこない…
そんな行動には、ちゃんと理由があります。
猫にとって“隠れる”ことは、怖さから身を守るための自然な行動。
安心できる場所があるだけで、「ここなら安全」と心を落ち着けることができるんです。
- カーテンの裏やベッド下など、暗くて狭い場所をそのまま残す
- お気に入りの毛布やタオルを入れたダンボール箱を置く
- 人の出入りが少ない静かな部屋を“避難所”にする
無理に出そうとせず、「隠れていても大丈夫」と見守ることが大切。
その安心感が、猫の心の回復をそっと支えてくれます。



「そこが、あなたの安心できる場所なんだね」
そう思って見守るだけで、猫の表情は少しずつ穏やかになりますよ。
②なるべく静かな空間をつくる
地震のあとは、ちょっとした音にも敏感になってしまう猫が多いんです。
いつもなら気にしない生活音にも、びくっと反応して隠れてしまうこともあります。
そんなときは、なるべく静かで落ち着ける空間をつくってあげることが大切。
人の声やテレビの音、ドアの開閉音などを少し控えるだけでも、 猫の緊張がすっとやわらぐことがあります。
- テレビや音楽のボリュームをいつもより下げる
- 来客や子どもの声が届きにくい部屋に猫を移す
- ドアの開け閉めを静かにするよう家族にも協力してもらう
静かな環境は、猫にとって“安全な空気を取り戻す時間”になります。
外の音が気になるようなら、カーテンを閉めて視界をやわらげてあげるのもおすすめです。



「音が少ない=安心できる」
その小さな気づかいが、猫の心を落ち着かせるいちばんの近道なんです。
③好物のおやつや食事で気を引く
怖い思いをしたあと、猫がごはんを食べなくなることは珍しくありません。
でも、それは“体調が悪い”というより心がまだ落ち着いていないだけのことが多いんです。
そんなときは、猫の「好きな味」「安心できるにおい」を使って、少しずつ気持ちをほぐしてあげましょう。
無理に食べさせる必要はありません。
においを嗅いだり、少し口をつけるだけでも前進です。
- いつもより香りの強いウェットフードを出してみる
- 大好きなおやつを手から少しだけ差し出す
- 食器の場所を静かなところに変えてみる
食べることは、「もう大丈夫かも」と感じるサイン。
焦らず、少しずつ食欲が戻ってくるのを見守ってあげましょう。



においを嗅いでくれた、それだけでも一歩前進。
小さな変化を、いっしょに喜んであげてくださいね。
④そっと近くにいるだけでOK
「怖がっている猫に、何をしてあげればいいの?」
そう悩む飼い主さんも多いですが、じつは“何もしない優しさ”もあるんです。
地震のあと、猫は少しの動きや音にも敏感になっています。
そんなときにベタベタ構うより、「そばにいる安心感」を感じさせてあげることが、
いちばんの心の支えになることもあるんです。
- 声をかけず、静かに近くの部屋で過ごす
- 視線を合わせすぎず、猫が落ち着くまで待つ
- 猫が自分から近づいてきたら、そっとなでる程度にする
大切なのは「一緒にいるよ」という空気。
それだけで、猫は“自分はひとりじゃない”と感じて安心できるんです。



言葉よりも、静かなぬくもりを。
あなたの存在そのものが、猫にとっての安心なんです。
⑤BGMや飼い主の声など好きな音を流す
静かな環境は安心につながりますが、“心地よい音”が猫の不安をやわらげてくれることもあります。
たとえば、飼い主さんの声ややさしい音楽。
それらは猫にとって「日常が戻ってきたサイン」になるんです。
特に、普段からよく聞いている声や音は安心の記憶として心を落ち着けてくれます。
- やさしいクラシックや自然音のBGMを小さな音で流す
- 飼い主さんの声を録音して流す、または穏やかに話しかける
- テレビを小音量でつけて“いつもの空気感”をつくる
大事なのは、音の“種類”よりも「いつも通りの空気」を感じさせてあげること。
安心できる音は、猫の心を少しずつリラックスへ導いてくれます。



あなたの声も、猫にとっては癒しの音。
穏やかに話しかけるだけで、安心がゆっくり広がっていきますよ。
⑥いつものおもちゃで軽い遊びを誘う
少しずつ落ち着いてきたら、“遊び”が心の回復サインになることもあります。
ただし、無理に動かそうとせず、猫のペースに合わせてそっと誘うのがポイントです。
地震のあとしばらくは、体も心も緊張しています。
だからこそ、遊びは“元気を出すため”ではなく、「安心して動けるようになるため」のきっかけとして取り入れてみましょう。
- お気に入りのじゃらしを、いつもよりゆっくり動かしてみる
- 少し離れた場所から軽く転がすボール遊びをしてみる
- 猫が近づいてこないときは、遊びを無理に続けない
“いつもの遊び”は、猫にとって日常の安心そのもの。
少しでも体を動かせたら、それだけで大きな一歩です。



「遊びたい」と思えたら、もう大丈夫のサイン。
焦らず、猫の笑顔が戻る瞬間を見守ってあげてくださいね。
⑦他の猫や人との接触は最小限にする
地震のあと、猫はとても神経が敏感になっています。
そのため、他の猫や人との接触が増えると、安心よりも不安が強まってしまうことがあるんです。
特に多頭飼いの家庭では、1匹が不安になると、他の子にも緊張が伝わることがあります。
一時的に距離を取ることで、お互いのペースを保ちやすくなります。
- 不安が強い猫は、別の部屋で静かに過ごさせる
- 知らない人や子どもが触れようとするのを控える
- 他の猫と一緒にするのは、落ち着いてから少しずつ
今は「群れ」より「ひとりの安心」を優先してOK。
静かな時間と空間が、猫の心をゆっくり回復へ導いてくれます。



ひとりで過ごす時間も、癒しのひとつ。
“安心できる距離”を守ってあげることが、いちばんの思いやりです。
まとめ|猫が地震後に様子がおかしいときに大切なこと
地震のあとに猫の様子が変わるのは、決してめずらしいことではありません。
それは、怖かった出来事を心の中で整理している最中なんです。
大切なのは、「元に戻す」ことを急がないこと。
“今の猫を受け入れてあげる”だけで、少しずつ安心を取り戻していきます。
- 隠れても、鳴いても、「怖かったんだね」と見守る
- 環境を変えず、静かに過ごせる空間を保つ
- 少しの食欲や行動の変化も、回復のサインと捉える
地震の記憶は、時間とともにやわらいでいきます。
焦らず、いつも通りの優しさで接していくことが、いちばんのケアになります。



あなたの落ち着いた声と優しいまなざしが、猫にとっての“安心の証”です。
今日もそっと寄り添ってあげてくださいね。


コメント