
「猫を飼いたいけど、ここ賃貸だし…大丈夫かな?」
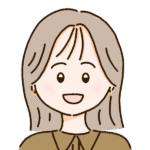
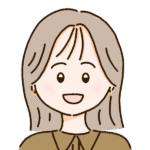
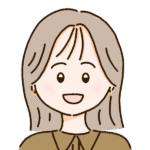
壁や床を傷つけたり、鳴き声やにおいでトラブルにならないか心配…



ペット可の物件だけど、実際どこまで自由にしていいのかわからない!
本記事で、そのようなお悩みをまるごと解決します。
私自身、賃貸で猫を飼い始めたときは不安だらけでした。
爪とぎ・におい・鳴き声・原状回復・ご近所トラブル…まさに「猫と賃貸って両立できるの?」という状態。
でも試行錯誤を重ねた今では、
猫も快適、人間も快適、そして退去時も安心な暮らしを実現できています。
「猫 賃貸 対策」は、むずかしくありません。
ほんの少し工夫を加えるだけで、猫も人もノーストレスで暮らせる環境は作れます。



この記事を読むことで、あなたも「猫との賃貸暮らし、全然大丈夫!」と心から思えるようになりますよ。
- 猫と賃貸で暮らすときによくある3大トラブル
- 初心者でもできる5つの対策
- 事前に知っておきたいペット可物件の落とし穴
- 実体験ベースのリアルな工夫とおすすめグッズ
猫と賃貸暮らし、ここが心配!よくあるトラブルと悩みとは?


猫と暮らしたいけど、ここは賃貸。
「ちゃんと飼えるかな?」「トラブル起きない?」と心配になりますよね。
この章では、猫×賃貸暮らしで実際によくある3つのトラブルについて、
事前に知っておくべき現実と解決のヒントをお伝えします。
壁・床・柱の爪とぎで原状回復費用が高額に?
猫の爪とぎによる壁・床の損傷は、賃貸暮らしで最も費用リスクが高いトラブルです。
なぜなら、猫にとって爪とぎは「本能的な行動」であり、
止めさせることはできないうえに、好みの場所を選んで行うからです。
以下のような事例は、実際によくあるパターンです。
- 壁紙の角がボロボロに裂けて、下地まで見えてしまった
- クローゼットのふちを毎日ガリガリされて木材が削れた
- フローリングの一部に爪痕がくっきり残り、張り替え費用を請求された
「爪とぎを買えば防げるんじゃない?」と思うかもしれませんが、
猫は素材・高さ・設置場所にこだわる生き物。
合わない爪とぎでは、他の場所で爪をといでしまいます。
だからこそ、傷を防ぐには“行動をコントロール”ではなく“環境を整える”ことが重要。



爪とぎの設置・保護シート・家具配置の工夫が、原状回復費用のリスクを大きく減らします。
鳴き声・におい・毛など、近隣トラブルの不安
賃貸での猫飼育では、騒音・におい・抜け毛による近隣トラブルが大きなストレス源になります。
というのも、集合住宅では音・におい・アレルゲンの「漏れ」が避けにくく、ペットに寛容でない住人も少なくないからです。
たとえば、以下のようなトラブル事例があります。
- 発情期の鳴き声が夜中に響き、壁の向こうから苦情が来た
- トイレのにおいがこもって、共用部まで臭うと言われた
- 換気不足で空気中の毛やアレルゲンが舞い、アレルギー持ちの隣人と揉めた
「うちの子は静かだし、そんなに問題ないでしょ」と思っていても、
体調・環境・ストレスなどで、急に鳴き始めることもあるのが猫という生き物。
騒音・におい・毛問題は、“起きてから対処”より“起きる前の対策”がカギ。



防音カーテン、空気清浄機、消臭剤などを駆使して、猫もご近所も快適な空間を目指しましょう。
実は多い!ペット可賃貸でも起きるトラブル例
「ペット可だから安心」と思い込んでいると、予想外のトラブルに巻き込まれることがあります。
というのも、「ペット可」という表記だけでは、
具体的にどの動物が・どの程度までOKか明確でないことが多いからです。
実際に起きがちなトラブルには、次のようなものがあります。
- 猫はOKだと思っていたら「小型犬のみ」と契約書に書かれていた
- 猫による壁や床の傷で、敷金が全額差し引かれた
- 猫の鳴き声やトイレ臭が原因で、隣人からクレームが入った
「ちゃんとペット可の物件を選んだし、大丈夫なはず」と安心したくなりますが、
契約内容や管理規約を細かく見ていないと、入居後に苦労するケースは少なくありません。



ペット可=無条件OKではないことを前提に、
物件選び・契約時点からしっかり確認しておくことが、後悔しないための最大のポイントです。
猫飼いが賃貸でできる対策はこれで完璧!初心者でもできる5つの基本


この章では、賃貸で猫を飼う初心者さんでも今日から実践できる、5つの基本対策を紹介します。
「爪とぎ・におい・鳴き声・逃走・設備保護」という5つのテーマで、
私が実際にやって効果を感じた方法をもとに解説していきますね。
爪とぎ対策は最優先!傷を防ぐグッズとしつけ法
爪とぎによる傷は“最初の1ヶ月”で決まると言っても過言ではありません。
なぜなら、猫は「どこで爪をとぐか」を早い段階で習慣化するからです。
以下は、私や知人が実際に使って効果があった対策グッズやしつけのコツです。
- 麻縄素材や段ボール素材の”縦型”爪とぎを壁際に設置(壁の保護にも◎)
- 爪とぎしたくなる場所に透明保護フィルムを貼る(100均で買えます)
- 爪とぎできたらおやつで「そこが正解だよ」と教える
「でもうちの子、しつけが通じる気がしない…」と感じる方も多いですよね。
でも実際には、“叱る”より“褒める”方が圧倒的に効果的なんです。



猫の行動は「その場所で気持ちよかったかどうか」で決まるので、
「ここでとげば褒められる、快適」と思わせられれば、他ではしなくなりますよ◎
におい&抜け毛対策は“習慣化”がカギ
においや毛の問題は「週1の掃除」ではどうにもなりません。
猫と暮らすうえで避けられないのが「トイレ臭・毛の飛散」などの“生活感”。
この問題を放っておくと、部屋全体に猫臭が染みついたり、ご近所トラブルの原因にもなりかねません。
我が家で定番となっている習慣はこちら。
- トイレ掃除は朝・夜の1日2回、必ず行う
- 1か月に1回、トイレを洗うか除菌シートで拭き上げる
- 空気清浄機を「24時間つけっぱなし」にしておく
- 掃除機は2日に1回はかける
「仕事で忙しくて、そんなこまめにできない…」という声もよく聞きますが、
実は慣れてくると「ながら掃除」感覚でできるようになります。



においと毛対策は、“がんばる”より“ルーティン化”が正解。
毎日のちょっとした積み重ねが、快適な部屋と心の余裕をつくります。
鳴き声対策は“生活音”でカバー
猫の鳴き声対策は「静かにさせる」よりも「気にならない環境をつくる」ことがポイントです。
なぜなら、猫は完全に無音の環境よりも、
人間の生活音があるほうが安心して過ごせる生き物だから。
特に夜間や留守中、無音状態になると、不安から鳴き続ける子もいます。
以下のような工夫で、鳴き声対策が可能です。
- テレビやラジオを「音量小さめ」でつけっぱなしにして外出
- 遮音カーテンやカーペットで部屋の防音性を高める
- 帰宅時に「大げさに反応しない」ことで要求鳴きを抑える
「でも音出しっぱなしって逆にストレスじゃないの?」と思うかもしれませんが、
テレビの話し声や日常的な生活音は“背景音”として猫に安心感を与えると言われています。
うちの猫も、人がいてテレビ音があるときの方がよく寝ています。



“無音=安心”ではなく、“音のある日常こそ安心”という考え方が、
鳴き声対策の第一歩です。
脱走・迷子は「○○対策」で8割防げる!
猫の脱走・迷子対策は「玄関&窓」の“2点ガード”でほとんど防げます。
というのも、室内飼いの猫が脱走する原因の8割以上は、
玄関のすき間 or 窓の開けっ放しからのすり抜け。
以下の対策を組み合わせることで、ほぼ完全に脱走リスクを封じることができます。
- 突っ張り式の玄関ゲートを設置する
- 網戸ロックや二重ロックで窓の開閉を制限する
- 首輪+迷子札(or マイクロチップ)を必ずつける
「うちの子は外に興味ないから大丈夫」と思っていても、
地震や来客、引越しなどの“突発的な出来事”でパニック脱走することが多いんです。
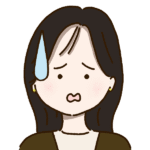
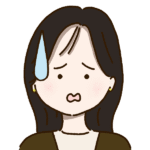
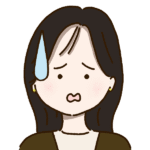
猫は想像以上に俊敏で、予想しないタイミングで飛び出します。
「念のため」ではなく「絶対に出さない前提」で、物理的なガードをしておきましょう。
壁・床・カーテン…設備保護には“先回り”が命!
賃貸の設備は「壊れてから対処」では遅く、先に保護しておくことが重要です。
なぜなら、猫のいたずらやマーキングは“ある日突然”始まることが多く、
傷や汚れがついてからでは原状回復が難しくなるからです。
以下は、私が実際に試して効果が高かった保護アイテムや工夫です。
- 壁:猫の通り道や角に透明の保護シートを貼る
- 床:フロアマットなどで床全体を保護する
- カーテン:丈を短めにして、じゃれつき防止+破れ防止
「まだ傷つけてないし、今は大丈夫そう」と思って油断していると、
突然のテンションMAXタイムや、発情期の行動で一気にダメージを受けることも。



“何もしない”のではなく、“壊れる前に防ぐ”のが賃貸猫暮らしの鉄則。
100円グッズや突っ張り棒などでも十分対策できますよ◎
ペット可物件選びで見落としがちな注意点


「ペット可」と書いてあっても、すべての物件が猫に優しいわけではありません。
この章では、契約前に見落とされがちな注意点を解説します。
ペット可=猫OKではない?見逃されがちな契約条件
「ペット可=猫OK」とは限らず、実は“猫NG”の物件も多いんです。
というのも、猫は犬よりも「壁・床を傷つけるリスクが高い」と見なされているため、
契約上は“ペット可”でも猫だけが禁止されていることがよくあります。
見落としがちな契約条件の一例はこちらです。
- 重要事項説明書に「小型犬のみ」と記載がある
- 「多頭飼育・猫は禁止」とただし書きがある
- 申込時に「猫は爪が…」と管理会社が渋る
「でも、不動産屋さんがOKって言ったから…」と安心してしまいがちですが、
口頭のやりとりは証拠にならないため、後々トラブルになることも。



契約時は、猫がOKかどうかを必ず書面で明記してもらうことが鉄則です。
入居前に確認すべき3つのチェックポイント
物件を選ぶときは「ペット可」だけでなく、“住みやすさ”の条件も確認が必須です。
猫との暮らしでは、意外なところにストレスやトラブルのタネが隠れています。
特に以下の3つは、実際に住み始めてから「見ておけばよかった!」と後悔しやすいポイントです。
- 窓やベランダの安全性(脱走防止の工夫がしやすいか)
- 床の素材(爪で傷つきやすいフローリングかどうか)
- 近隣のペット飼育率(気兼ねせずに暮らせるか)
「とにかく早く決めたい!」と焦ってしまう気持ちもわかりますが、
猫との暮らしは日常そのもの。
毎日を快適に過ごすためにも、慎重にチェックを。



「物件選び=猫のQOLを決める」と思って、下見や内見での確認を怠らないようにしましょう。
ペット共生型との違い|本当に暮らしやすいのはどっち?
「ペット可」と「ペット共生型」はまったく別物で、後者のほうが圧倒的に暮らしやすいです。
その理由は、ペット共生型は「ペットと暮らす前提」で物件が設計・管理されているからです。
例えば、以下のような違いがあります。
- 専用のキャットウォークなどが設置されている
- 防音・消臭・傷防止に配慮された壁や床材が使用されている
- 近隣住民も全員ペット飼育者なので気兼ねがない
「でも、共生型って家賃が高そう…」と感じる方もいるかもしれません。
確かに若干割高なこともありますが、修繕費やトラブル対策を考えると結果的に割安になるケースも多いです。



猫との快適な暮らしを重視したいなら、共生型物件を一度検討してみる価値は大いにあります。
退去時トラブルを防ぐ原状回復テクニック


賃貸で猫を飼うと、どうしても心配になるのが「退去時の原状回復費用」ですよね。
この章では、トラブルになりがちなポイントと、その予防策を紹介します。
敷金が戻らない理由No.1は「爪とぎ跡」だった!
敷金が返ってこない最大の理由は、「猫の爪とぎによる壁や柱の傷」です。
猫の本能である爪とぎは止めさせることが難しく、
壁紙や柱がボロボロになると「借主負担」での修繕対象になります。
私も実際に敷金がほとんど戻らない、ってことが何度もありました。
退去時に見られるポイントは、主に以下のような場所です。
- 壁紙のひっかき傷・汚れ
- 床の傷やへこみ
- 猫の体臭や尿の臭い残り
「うちの子はあまり爪とぎしないから…」という油断が一番危険。
引越し前になってから焦るパターンは本当に多いので、対策は早ければ早いほど◎です。



敷金を守るためには“猫の習性に合わせた先回り”が最重要ポイント!
退去前にやっておくべき「現状確認」と交渉術
退去前には「どの範囲までが借主負担になるか」を、事前に確認しておくことが重要です。
というのも、管理会社によって原状回復の基準は異なり、
放っておくと「全部請求される」ことも珍しくないからです。
私が実際にやっておいてよかったと感じた現状確認・交渉方法は次の3つです。
- 入居初日に室内を撮影しておく(もともとキズがあれば記録しておく)
- 経年劣化かどうかの判断を国交省ガイドラインで照合する
「なんとなく高額を請求されそうで怖い…」という方も多いですが、
事前に状況を説明したり、証拠を残しておくことで交渉は意外とスムーズに進みます。



退去直前になって焦らないためにも、“自分から動く”ことがトラブル回避の最大のコツです。
猫も人も心地いい!賃貸暮らしの工夫アイデア集


猫との賃貸暮らしは、ちょっとした工夫でグッと快適になります。
この章では、私自身がやって「これは良かった!」と感じたアイデアを紹介します。
狭くても快適!猫が落ち着ける居場所づくりのコツ
猫が安心して過ごせる“自分の居場所”を作るだけで、問題行動が激減します。
というのも、猫は本能的に「安心できる隠れ家」を必要とする動物だからです。
狭い賃貸でもできる“猫の居場所づくり”のアイデアは以下の通りです。
- カラーボックスを横倒しにして毛布を敷く簡易ハウス
- ベッド下やクローゼットに布で囲いを作る隠れスペース
- 窓際に猫ベッドを設置して日向ぼっこスポットに
「部屋が狭くてそんなスペースないよ…」という方も、
家具の“すきま”や“上”を活用すれば意外と作れることが多いです。



猫にとって「落ち着ける場所」があることは、精神的な安定にも直結します。
音やにおいに配慮してストレスを減らすテクニック
猫はとても敏感な動物。音やにおいのストレスは、体調にも影響します。
特に賃貸住宅では、生活音やにおいの逃げ場が少ないため、
飼い主が意識して配慮することが大切です。
私が実際にやって効果的だった工夫は以下の3つです。
- 掃除機・テレビなどの大きな音を出すときは猫を別室に移動
- 芳香剤や洗剤は「無香料」か「ペット用低刺激」にする
- 猫トイレは風通しのいい場所+消臭マットで臭いを拡散させない
「うちの子は大丈夫そうだから」と思っていても、
猫は不調を隠すのが得意。
体調を崩してから気づく前に、ストレス源は減らしておきましょう。



人にとって快適=猫にも快適とは限りません。
猫視点での工夫が大切です。
インテリアと猫グッズを両立するアイデア実例
猫グッズは「置いてるだけで浮く…」と思われがちですが、選び方と工夫次第で部屋になじませることができます。
というのも、最近ではおしゃれなデザインの猫アイテムがたくさん出てきているからです。
私が実際に使ってよかった「インテリア映えする猫グッズ」はこちらです。
- 北欧風の木目調キャットタワー(棚っぽく見えて圧迫感ゼロ)
- 無印・ニトリの収納ボックスを活用した猫ハウス
- カゴ型ベッドやラタン風素材でナチュラル系インテリアに馴染む
「部屋がごちゃごちゃになるのがイヤ」という方も、
“生活感を出さずに猫グッズを取り入れる”ことは十分可能です。



猫も人も快適に暮らせる空間は、“ちょっとした工夫”でちゃんと作れます◎
まとめ|賃貸でも工夫すれば猫と心地よく暮らせる!
今回は「猫 賃貸 対策」というテーマで、猫を飼い始めたばかりの方に向けて、
実際のトラブル事例から暮らしの工夫までを網羅的にご紹介しました。
最後に、猫との賃貸暮らしを安心して楽しむためのポイントをおさらいします。
- 「ペット可=猫OK」とは限らない!契約書は必ず確認
- 壁・床・柱のキズ対策で、敷金トラブルを防ぐ
- 猫の居場所・快適空間づくりで問題行動を予防
- 臭いや音への配慮は、猫にも近隣にも大切
- 退去前には現状チェックと証拠保全を忘れずに
「猫を賃貸で飼うのは大変そう…」と感じていた方も、ポイントを押さえれば心配ありません。
工夫しながら暮らしていく中で、きっと猫との距離も、もっともっと近くなっていきますよ◎



あなたと猫ちゃんの毎日が、もっと楽しく心地よいものになりますように。
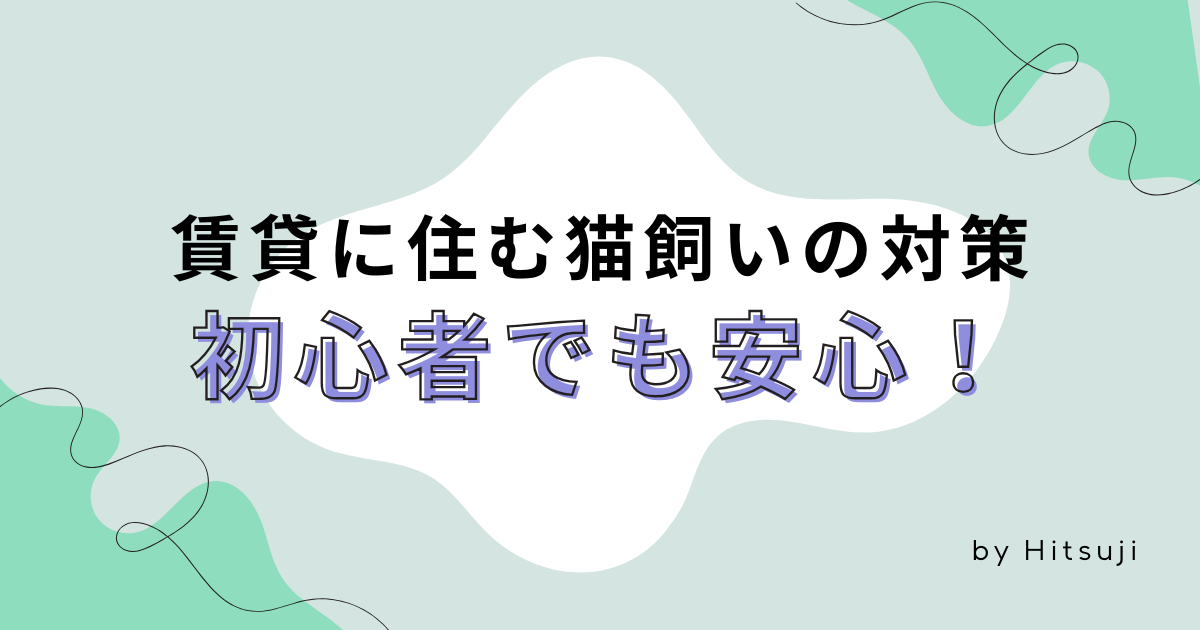
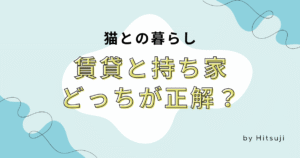
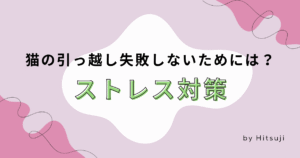
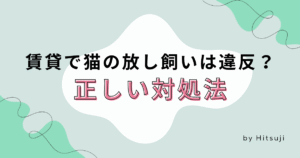
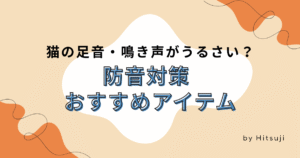
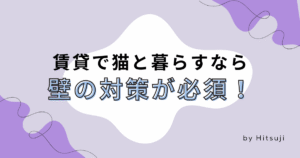
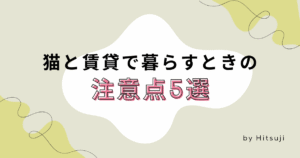

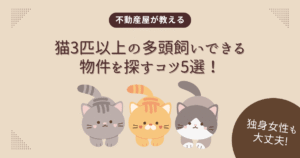
コメント