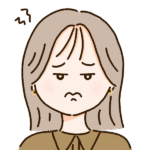
猫の爪とぎで壁や床を傷つけないか心配…



鳴き声がうるさいと近隣トラブルになりそう



そもそも猫OKの物件がなかなか見つからない~!
そんなお悩みをこの記事で解決します。
実は、猫と賃貸で暮らすには“見えない注意点”がたくさんあるんです。
ペット可の物件だからといって、何も気にせず住めるわけではありません。
筆者は元・動物看護士で、現在は2匹の猫と一緒に賃貸で暮らしています。
実際に住んでみてわかった「これは気をつけておけばよかった…!」という経験もたくさん。
この記事では、そんなリアルな視点から、
猫と賃貸で快適に暮らすための注意点を5つにまとめてお伝えします。



「これから猫と暮らしたい」
「すでに一緒に住んでるけど、トラブルが不安…」
という方も、ぜひ参考にしてくださいね。
猫を賃貸で飼うときに知っておくべきこと3つ
「ペット可って書いてあるけど、ほんとに猫もOK?」
「あとからトラブルにならないか心配…」
そんなモヤモヤを感じている方、多いのではないでしょうか。
この章では、「猫を賃貸で飼うとき、何に気をつければいいのか?」という不安に対して、
最初に必ず確認しておきたい3つのポイントを解説します。
そもそも「ペット可」でも猫NGな賃貸がある理由
「ペット可=猫OK」ではない。
これが、最初に知っておくべき事実です。
実は、ペット可物件の中には「小型犬はOKだけど猫はNG」というケースが意外と多くあります。
なぜなら、以下のような理由で禁止されているからです。
- 猫の爪とぎによる壁・柱の損傷が深刻
- マーキングによるにおい残りが強い
- 集合住宅では鳴き声による苦情も多い
つまり、「ペット可」とだけ書いてあっても、必ず猫OKかどうかを確認する必要があるということです。
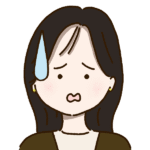
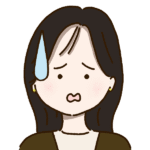
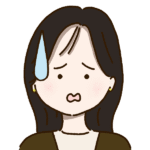
実際に物件の問合せをしても、
「犬はOKだけど猫はダメ」と言われたこと、何度もあります…
ペット相談可とペット可の違いを正しく理解しよう
「ペット可」と「ペット相談可」は、似ているようで全く別物です。
ざっくり言うと、以下のような違いがあります:
- ペット可:ルールを守れば、原則OK(ただし種類制限あり)
- ペット相談可:ペットを飼いたい旨を申し出て、大家の許可を得る必要がある
つまり、「ペット相談可」は審査・条件付きOKのニュアンス。許可が下りるかどうかは大家さん次第です。
トラブルを防ぐためにも、「相談可=いける!」と思い込むのはNG。
必ず事前に確認を取り、書面にも残しておきましょう。



物件を探すときに、不動産屋の担当者に忘れず確認しておきましょう。
大家・管理会社に確認すべき具体的なチェック項目とは?
先述しましたが、
契約前には「猫に関して具体的にOKな内容」を、
大家さん・不動産屋の担当に明確に確認しておくことが大切です。
- 猫の飼育が明記された契約書(犬のみOKなどの除外条項がないか)
- 頭数制限の有無(1匹まで、2匹までなど)
- 追加の敷金・礼金が必要かどうか
- 退去時の原状回復条件(壁紙・床の破損基準など)
これらを事前に確認し、書面に残しておくことで、トラブルの9割は未然に防げます。
「大丈夫ですよ〜」の口頭確認ではなく、必ず書面で証拠を!
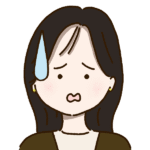
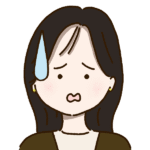
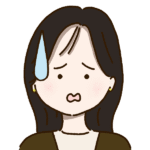
書面に残しておかないと、
過去に「言った言わない」でモメるか、泣き寝入りするかの2択になってしまいます。
猫と暮らす賃貸物件を選ぶときの5つの注意点
「ペット可の物件を見つけた!…けど、猫と暮らすには本当に適してる?」
そんなときにチェックすべき5つのポイントをご紹介します。
見落とされがちですが、
猫の性質と生活パターンを考慮した物件選びが、のちのトラブル防止と快適な暮らしに直結します。
- においや毛が残りやすい壁紙・床材に注意
- 爪とぎによる傷つきやすい場所をチェック
- 鳴き声対策になる「遮音性のある物件」とは?
- 脱走防止できる構造か(窓・玄関・ベランダ)
- 将来の引っ越しも見越して考えるべきこと
注意点①においや毛が残りやすい壁紙・床材に注意
猫との生活は「におい」と「毛」との戦いとも言えます。
特に注意すべきは、床材や壁紙の素材。
賃貸でよく使われている安価なビニールクロスやフローリングは、
- 毛がからまりやすい
- においが染み込みやすい
- 掃除しても完全に落ちないケースがある
こうした素材は、退去時の原状回復費用が高くなる原因にもなります。
できれば、クッションフロアや防臭性のある壁材など、
掃除しやすく劣化しにくい素材を使っている物件がおすすめです。



そもそも猫可の物件が少ない中で多くは望めませんが、
内見時に気にとめておくと◎
見てもわからない場合は、不動産屋の担当に聞いてみましょう。
入居してからできる床対策はこちらで詳しく解説しています。⇩
注意点②爪とぎによる傷つきやすい場所をチェック
猫といえば、爪とぎ。
特に壁の角・柱・扉まわりは要注意です。
内見の際には、以下のような場所に引っかき傷がつきやすいかをよく見てみましょう。
- 壁紙が柔らかく、簡単に剥がれそう
- お部屋の間取りに壁の角が多い
- 木材のドア・枠がむき出し
こうした場所は、猫の本能的な「研ぎたい衝動」を引き出してしまいます。
対策としては、縦型爪とぎ・保護フィルム・爪とぎ防止シートなどを事前に用意しておくのが鉄則です。



私も飼い初めのころは対策しておらず、
壁がズタボロになって、敷金をごっそり持って行かれました…!
我が家でバリバリ活躍している爪とぎがこちら⇩
注意点③鳴き声対策になる「遮音性のある物件」とは?
猫は静かなイメージがあるかもしれませんが、
意外と鳴き声で苦情が来ることもあります。
特に、夜中やお留守番中に大声で鳴く子は、近隣住民とのトラブル原因に。
- 鉄筋コンクリート(RC)構造の物件
- 戸境壁が分厚い部屋(隣と接していない間取り)
- 2階以上の角部屋
これらの物件は、音のトラブルを最小限に抑えてくれます。
音漏れは「住んでみないとわからない部分」だからこそ、内見時の耳チェックが超重要です。
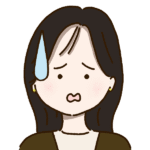
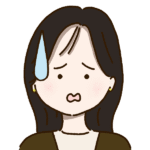
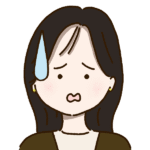
うちは鉄骨鉄筋コンクリートなので今のところ苦情はありません。
でも木造アパートに住んでいたときは、大家さんづてで怒られました…
注意点④脱走防止できる構造か(窓・玄関・ベランダ)
猫との暮らしで意外と多いトラブルが脱走・転落事故。
とくに賃貸では、玄関・窓・ベランダの作りをしっかりチェックすることが大切です。
- 窓に網戸があるか(外れやすくないか)
- ベランダに猫がすり抜けられる隙間がないか
- 玄関からの飛び出しを防げる間取りか
また、もし玄関から飛び出してしまっても共用の廊下があればセーフ。
玄関を開けた目の前の道に車が通る物件だと、かなり危険です。



玄関に飛び出し防止の柵を取り付けることで、事故を防げます。
キッチンの入り口などにもおすすめです。
我が家で使用している柵はこちらです⇩(取付簡単なのでガチおすすめです)
注意点⑤将来の引っ越しも見越して考えるべきこと
今は住めても、数年後に猫がいることで引っ越し先が見つからない…
というケースも珍しくありません。
長く安心して暮らすためには、「次の住み替え」まで見据えるのが◎
- 今住んでいる物件の更新・退去ルールを確認
- ペット可のエリア・家賃相場を事前に把握しておく
- 猫の頭数制限がある物件が多い点に注意(ほとんど2匹まで)
「引っ越しできない…」と詰まないよう、事前に備えておくことが猫の幸せにもつながります。
猫と暮らす=長期目線が必要!
今だけでなく、将来の住環境も視野に入れましょう。



「猫可」物件って本当に少ない…。
だからこそ、次の選択肢も想定しておくと安心です!
猫3匹飼いのときの物件選びは、こちらで詳しく解説しています。⇩
猫と賃貸で暮らすためのトラブル予防法3選
猫と賃貸で暮らすうえで、「傷・におい・音」の3つは避けて通れない課題です。
でも、ちょっとした工夫や予防策で大家さんや近隣とのトラブルを防ぐことができますよ。
この章では、トラブルを未然に防ぐための対策を3つに分けて紹介します。
予防法①壁や床の傷をつけさせない予防をする
猫の爪とぎやジャンプによる傷は、
「特別損耗」とみなされて原状回復費用が高額になることも。
次のような対策で防止しましょう。
- 爪とぎシート・壁保護フィルムを設置
- 家具の角や柱に透明ガードを貼る
- ラグやカーペットで床の傷・音を軽減
爪とぎの場所を3〜4ヶ所に限定し、他の場所ではさせないしつけも効果的です。
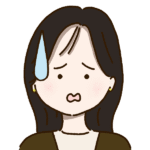
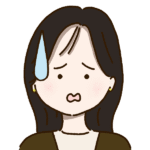
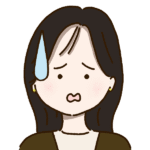
壁紙の張替え費用、想像以上に高いので要注意…!
予防法②夜泣きや発情期などの鳴き声トラブルを防ぐ
猫は静かな印象がありますが、
夜中に鳴く・発情期の声が大きいなどで苦情が入ることもあります。
以下の対策が有効です。
- 窓やドアの隙間に防音テープを貼る
- 鳴く時間帯を把握し、遊びで発散させる
- 避妊・去勢手術で発情期の鳴き声を防ぐ
また、壁の厚み・構造(木造かコンクリートかなど)も事前に確認し、音漏れしにくい部屋を選ぶことが大切です。



防音カーテンや2重窓も、けっこう効果ありますよ!
予防法③猫トイレの臭い対策
トイレの臭いは、玄関や共有スペースに広がってトラブルの原因になることも。
におい対策は「猫の健康」と「人間関係」両方に大きな影響があるので、重点的にケアしましょう。
- 脱臭機 or トイレ専用の空気清浄機を設置
- こまめなトイレ掃除+砂の総入れ替え
- 消臭効果の高い猫砂を選ぶ
また、換気扇やサーキュレーターの設置もにおい対策として有効です。



うちは猫トイレの近くに「トイレ用プラズマクラスター」置いてます。
我が家の猫砂は紙製を使っています。
紙製の猫砂でおすすめはこちら。⇩
まとめ|賃貸でも猫との暮らしを楽しむために
賃貸で猫と暮らすには、ルールや配慮が必要ですが、
ちょっとした工夫で快適な共生はじゅうぶん可能です。
今回ご紹介したポイントをおさらいすると、以下のとおり。
- 「ペット可」の中身は契約書で細かく確認する
- 内覧では周辺環境・音・構造もチェック
- 壁や床、においや鳴き声などの対策を徹底する
- ご近所・大家さんとの関係性も丁寧に築く
猫の習性を理解し、先回りした対策をしておくことが、賃貸トラブルを防ぎ、安心して暮らせるコツです。
筆者も最初は不安だらけでしたが、
今では「猫と暮らすからこそ、家がもっと大好きになる」
そんな毎日を送っています。
この記事が、あなたと猫ちゃんの“安心して暮らせる賃貸ライフ”のヒントになりますように。



賃貸でも、猫との暮らしはちゃんと叶います。
焦らず、楽しみながら工夫していきましょう◎
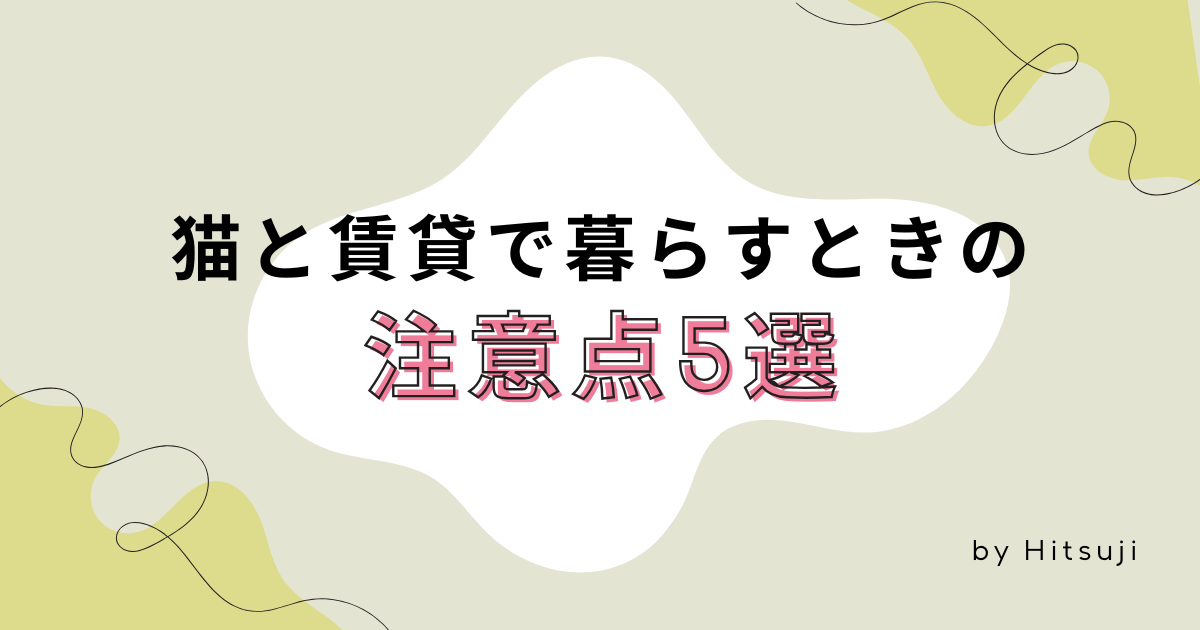



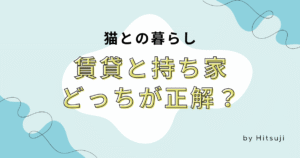
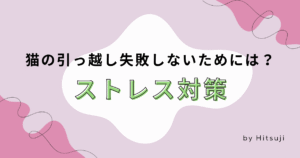
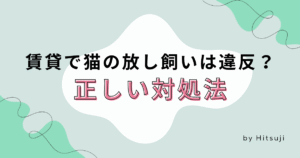
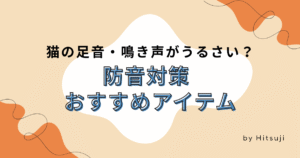
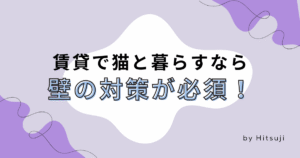

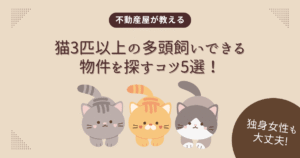
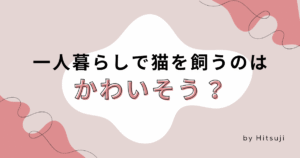
コメント